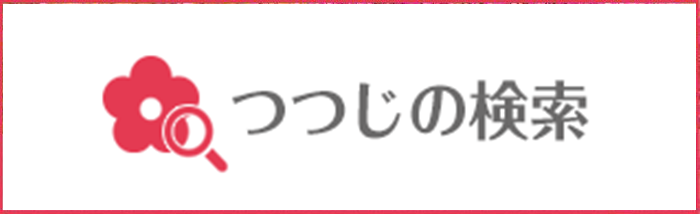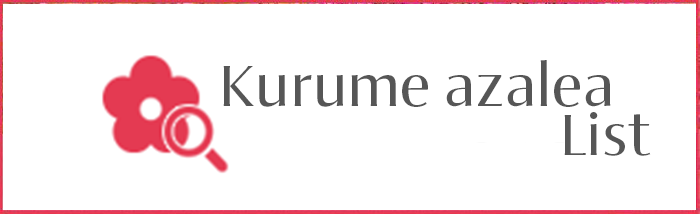久留米つつじ ゆかりの人々
坂本元蔵(1785-1854年) 久留米藩士

坂本元蔵(さかもと もとぞう)は、霧島つつじ(現在の江戸キリシマの仲間)を栽培していました。そのとき、もっと色々な花色の品種がほしいと思いました。そこで、久留米市の梅林寺や高良大社に行き、霧島つつじの種子を採り、播種しましたが、発芽しませんでした。
ある日、庭の苔の中にツツジの実生を見つけ、苔に種子を蒔くと発芽すること(苔蒔き法)を思いつきました。ツツジの実生繁殖法を知った坂本は、霧島つつじにはない花色をもつ新しい品種を作りました。これが久留米つつじの始まりです。
また、坂本は久留米つつじを広めるため、同好の人たちに新品種を分け、苔蒔き法を教えました。その結果、久留米つつじの品種数は、幕末に200に達しました。
初代 赤司喜次郎(1842-1920年) 赤司廣楽園園主

初代赤司喜次郎(あかし きじろう)は、赤司廣楽園を1873年に開園しました。坂本元蔵が所有していた久留米つつじ品種を収集するとともに、新品種を作りました。「久留米躑躅」という名称も作りました。
大正時代には、横浜植木株式会社の協力のもとアメリカやイギリスへの輸出に力を注ぎました。1905年には「久留米躑躅誌」を発行しました。この冊子には、坂本元蔵のことや江戸時代の品種(154品種)などが記載されていて、現在、わたしたちが久留米つつじの歴史を知るための重要な資料になっています。
アーネスト・ヘンリー・ウィルソン(1876-1930年) プラントハンター
ウィルソンは、ハーバード大学アーノルド植物園からの要請で、1914年(大正3年)にシダ植物、ツツジ、サクラを収集する目的で来日しました。このとき、東京幡ヶ谷の園芸店で、久留米つつじを初めて目にします。
1917年に再び来日したとき、横浜植木株式会社で久留米つつじに再会し、久留米つつじ発祥の地を訪れたいと思うようになりました。この希望は1918年に実現し、赤司廣楽園(久留米市東町)を訪問しました。ウィルソンは、赤司廣楽園で久留米つつじ48品種(実生1個体を含む)と、江戸キリシマ2品種を購入し、アメリカに送りました。これらの品種は、現在「Wilson 50」と呼ばれています。